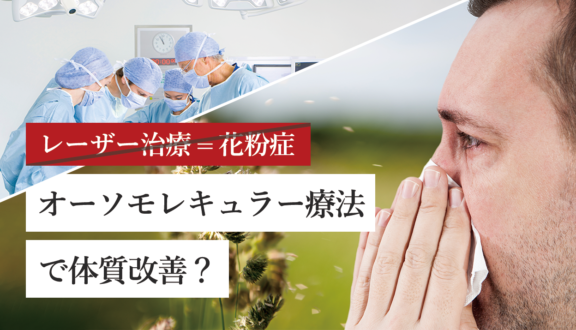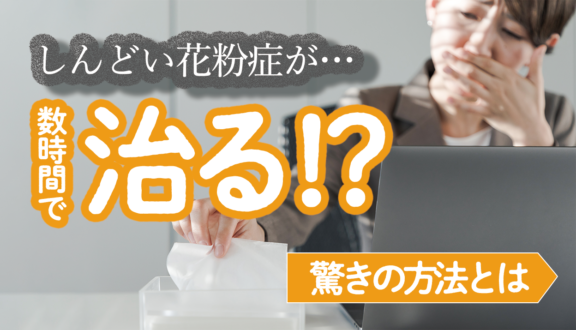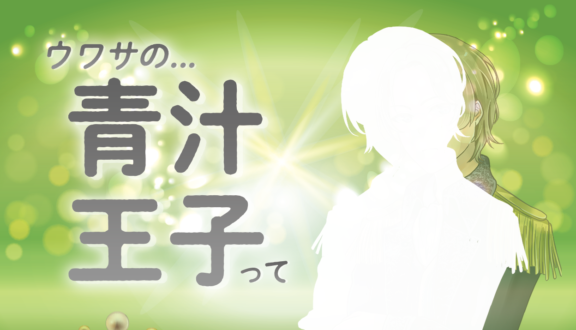【花粉症の特効薬?】食生活で体質改善
いまや国民病といわれる花粉症。これまでにさまざまな治療法が登場していますが、実は花粉症は食生活で改善することができるのはご存じでしょうか?
今回はこのつらい花粉症とセルフケアの方法について詳しくご紹介します。
花粉症のメカニズムを知り、効果的な対処法を行いましょう。
花粉症の原因は免疫細胞の誤作動
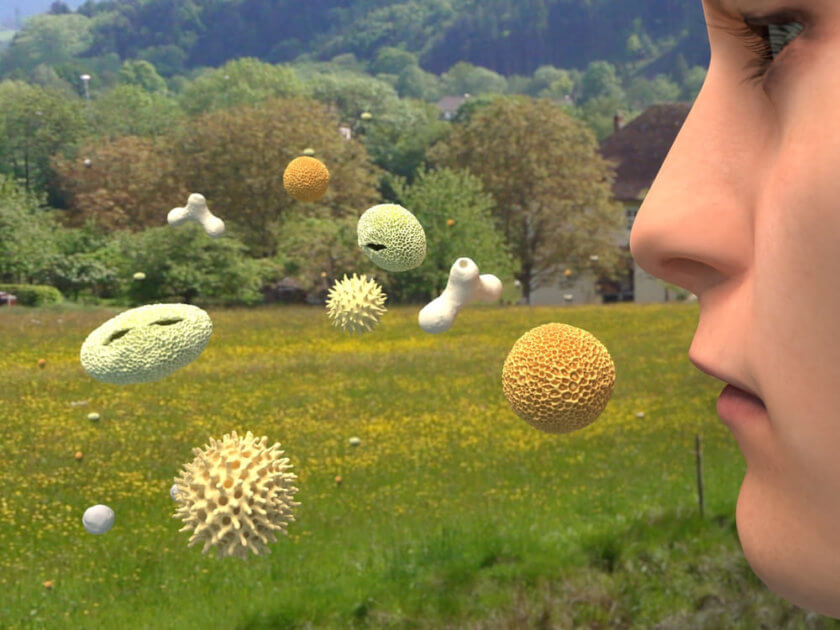
花粉症がおこる原因は、私たち人間の体の中にある免疫細胞の暴走によるものです。
本来であればスギやヒノキ、ブタクサなどの花粉は人間の体に害を与えるものではありません。
しかし何らかの理由で免疫システムが正常に機能していなければ、これらの花粉を有害物質と認識してしまい体内から追い出そうと過剰な反応を起こします。
これが鼻水や涙、くしゃみなどのアレルギー反応となります。
花粉症はⅠ型アレルギー
花粉症は即時でアレルギー反応を起こすため、Ⅰ型アレルギーに分類されます。
魚介類やスズメバチなどで起こる「アナフィラキシーショック」もこのⅠ型アレルギーと同じです。
花粉症の人の場合、花粉が目や鼻から入ってくると体の中のリンパ球が花粉を有害物質と判断し「Ige抗体」という物質を作り出します。
再び花粉が入ってくると、このIge抗体が反応し、花粉を追い出そうとするヒスタミンを大量に分泌。
するとこのヒスタミンが鼻や目の神経を刺激し、アレルギー症状を引き起こすのです。
花粉症はなぜ増えたのか

花粉症患者は戦後から急激に増え、現在では4人に1人の割合で発症しています。
その背景にはさまざま要因が推測されており、以下の説が濃厚だと考えられています。
1.戦後復興のためのスギ植栽
戦後、日本は復興のために焼け野原となった各地に大量のスギを植えます。
このことが物理的にスギ花粉患者を増やした要因と考えられています。
実際に花粉症患者の約7割がスギ花粉によるもので、スギ植栽が行われなかった北海道と沖縄の有病率はごくわずかな数となっています。
2.住環境の変化
風通しの良い木造の住宅が減り、気密性の高いマンションや戸建てが増えたことも花粉症患者が増えた要因と考えられています。
気密性の高い室内は快適ですが、花粉やハウスダストが部屋にこもりやすくなっています。
さらに温度と湿度が高くなるためカビやダニが繁殖しやすくなります。
花粉症やアレルギー体質の方は普段から換気や掃除を習慣づけるようにしましょう。
3.抗生物質の普及
抗生物質は20世紀の最大の発明といわれ、研究者には過去3人ノーベル賞が送られています。
その効果は絶大で、ウイルスなどの感染症やさまざまな病気から多くの人を守ってきました。この抗生物質の普及が花粉症患者が増えた要因のひとつとして考えられています。
実は抗生物質は有害なウイルスや細菌から私たちを守ってくれる反面、無害な腸内細菌まで排除してしまうことがあります。
そのため抗生物質を服用すると腸内フローラが乱れやすく、腸内環境が悪化する可能性があります。
抗生物質を服用する時は、フラクトオリゴ糖などの善玉菌のエサとなる食品をしっかり摂り、腸内フローラを守るよう心がけましょう。
4.衛生面の変化
ひと昔前に比べて近年では衛生面がクリーンになり、ウイルスや細菌に対する免疫が活躍することは少なくなっています。
本来であればウイルスに対する免疫とアレルギーに対する免疫が同じくらいのバランスであるのが理想的とされています。
しかしウイルスや細菌に対する免疫が少なくなると、どうしてもアレルギーに対する免疫が過剰に反応しやすくなるといわれています。
炎症はすべての病気の根源
実は、花粉症に限らず全ての病気は体の中で炎症が起こっている状態のことで、炎症の原因と場所の違いによって病名が異なっているだけなのです。
例えば、うつ病は脳の炎症によるもので慢性的なストレスが原因とされています。
その他にもがんや関節リウマチ、橋本病なども全て炎症によるものなのです。
食生活で炎症の起こらない体質へ

残念なことに、人間の体はこれらの炎症を抑える機能を持ち合わせていません。
そこで重要となるのが免疫システムが正常に作動させ、炎症が起こらないようにすることです。
どのようにすれば免疫システムは正常に働いてくれるのでしょうか?
以下で、その方法について順番にまとめてみました。
秘密の鍵は腸内環境
炎症の起こりにくい体質になる方法は非常にシンプル。腸内環境を整えれば良いのです。
実は腸壁には体全体の7割を占める免疫細胞が存在しています。
生活習慣や食生活などで腸内環境が悪化すると、自然と免疫力も低下してしまうのです。
もちろん免疫力が低下すると免疫システムも正常に働いてくれないため、本来無害な物質も誤作動により有害物質と判断されやすくなります。
このような状態になってしまうと花粉症やアトピーなどのアレルギー疾患だけでなく、リウマチなどの自己免疫疾患や感染症などのリスクが高くなってしまう可能性も。
最近体調がなんとなく優れないとお悩みの方は便秘や下痢が続いていないか、いま一度見直してみましょう。
腸脳相関とは
腸内環境は、免疫力だけでなく自律神経にも大きな影響を与えるのはご存じでしょうか。
食道から胃、小腸、大腸と腸管全体の壁内には数億個にも及ぶ神経細胞がネットワークのように網目状に張り巡らされています。
このつくりのおかげで、脳からの指令がなくても独自で腸を働かすことができ「第2の脳」と呼ばれています。
これらの神経細胞は自律神経の一部となるため、ストレスなどで脳に不快感を覚えると腸の蠕動運動が悪くなり便秘や下痢になりやすくなります。
反対に副交感神経が優位になりリラックス状態になると、蠕動運動が活発になり便意を促しやすくなります。
この関係を「腸脳相関」と呼び、自律神経を整えることが腸内環境と脳のバランスにつながるといって良いでしょう。
つまり腸脳相関の仕組みを賢く活用すれば、誰でも簡単に体調管理を行うことができるのです。
腸内環境を整える食生活とは?

では実際にどのような方法が腸内環境を整えるのに効果的なのでしょうか?
以下でおすすめの方法をまとめてみました。
少し根気はいりますが、誰でもできる方法なので是非試してみて下さい。
フラクトオリゴ糖で善玉菌が育ちやすい環境に
腸内環境を整えるためにおすすめしたいのがフラクトオリゴ糖。
大腸に存在する有益菌のエネルギー源となる「酪酸菌」を作り出すことができます。
乳酸菌やビフィズス菌、フラクトオリゴ糖などによって善玉菌は食物繊維をエサにして増殖し、腸内を弱酸性に保つ「酸」を作りだします。
腸内の弱酸性が保たれると、悪玉菌の発生が抑制され腸内フローラが整います。
腸内環境を整えるには乳酸菌やビフィズス菌の方が、効果が高いイメージがありませんか?
実は、乳酸菌やビフィズス菌は外殻をもっていないため、半数以上が胃酸で溶けてなくなってしまいます。
対して酪酸菌は「芽胞(がほう)」と呼ばれる外殻を持っているため、大腸までしっかりと届き、他の善玉菌が繁殖しやすい環境を作ってくれるのです。
今まで乳酸菌やビフィズス菌しか知らなかった方は、酪酸菌をつくってくれるフラクトオリゴ糖にも注目してみましょう。
プロバイオティクスとプレバイオティクス
乳酸菌やビフィズス菌は「プロバイオティクス」と呼ばれ、腸内フローラのバランスを整える細菌を含んだ食品のことを指します。
その健康効果は高く、整腸作用をはじめ感染予防、炎症性腸疾患の抑制、免疫調整作用などが認められています。
ただしプロバイオティクスは腸内にとどまることなく便と一緒に排泄されてしまうため、継続して摂取が必要となることを忘れてはなりません。
「プレバイオティクス」は自ら善玉菌のエサとなり、大腸内で善玉菌の働きをサポートしながら悪玉菌の増殖を抑制してくれます。
今回ご紹介したフラクトオリゴ糖や水溶性食物繊維の一部などがプレバイオティクスを含む食品として認められており、ヒトの消化能力では分解・吸収しにくいのが特徴といえるでしょう。
近年ではこのプロバイオティクスとプレバイオティクスの食品を一緒に摂取する「シンバイオティクス」が注目を浴びています。
腸内環境を本格的に整えたい方はシンバイオティクスを積極的に取り入れてみましょう。
ビタミン類を意識して摂取しよう
美肌ビタミンと呼ばれるビタミンCやB2、B6は、悪玉菌の増殖を抑制し、ビフィズス菌の増殖を助けてくれるため腸活にも有効です。
反対に善玉菌の働きによって、これらのビタミン類に加えビタミンKや葉酸などが生成されることもさまざまな研究データでわかっています。
善玉菌とビタミンの相乗効果を利用すると、腸活と美容に嬉しい効果が期待できそうですね。
あわせて糖質制限を行うとベスト
糖質を摂取し過ぎると、さまざまな生活習慣病を招く原因となることもあるので注意しましょう。
糖質の過剰摂取で血糖値が急上昇すると、血糖値を下げるためにインスリンが大量に分泌されます。
インスリンは糖を中性脂肪として溜め込む性質があるため、結果的に肥満や動脈硬化などを起こしやすくなるのです。
糖質制限を行うと、血中のブドウ糖の代わりに脂肪酸から作られるケトン体がエネルギー源となってくれるため良いこと尽くし。
体内の中性脂肪も燃焼しやすくなり、肌荒れ予防など美容にも嬉しい効果が期待できます。
ただし、完全に糖質などの炭水化物をシャットアウトしてしまうと善玉菌のエサとなる食物繊維の摂取量までも減ってしまい、腸内環境が悪化する可能性があります。
糖質は完全に制限するのではなく、白ごはんの代わりに食物繊維の多い根菜類や玄米、オートミールなどを代用してみましょう。
プラス生活習慣でより健康的に

腸内環境を整えるには、食生活だけでなく規則正しい生活や適度な運動も不可欠です。
腸内環境は自律神経からも大きく影響を受けるため、いくら食生活に気を配っていても睡眠不足や運動不足であれば腸の蠕動運動は低下します。
睡眠時間は5時間をきってしまうと交感神経が優位になり、自律神経が乱れる原因となります。110万人超の男女を対象に6年間行った米国の大規模調査では、毎日の睡眠時間が7時間の対象者がもっとも生活習慣病による死亡リスクが低いことがわかっています。
また適度な運動を行うとストレスを軽減するホルモン「セロトニン」や「エンドルフィン」が分泌され、リラックス効果が得られます。
リラックス効果が得られると副交感神経が優位になり、腸の蠕動運動が促されやすくなりますよ。
食生活にプラスして週3、4回は30分~1時間の運動、睡眠時間は7時間を目指しましょう。